坂内、座右の書
- orangejuku
- 7月8日
- 読了時間: 5分
塾長坂内推しの本、第一弾!
・・・と言いたいところですが、僕はあまり本を読みません。
読書家に見られることも多いですが実はあまり読んでいません。
そんな僕ですが、昔から
『ゲーテとの対話』(エッカーマン著、山下肇訳、1968~69)
という本が好きです。
岩波文庫で全3巻。
今でもちょいちょい読みます。
僕は子どもの頃から漫画家の故・水木しげるさんが好きで、
水木さんのエッセイに出てきたので
興味をもって読み始めたのです。
水木さんが若き日に文学青年を気取っていたころ、読んでいたとのこと。
ずいぶん昔から日本に紹介されていたんですね。
今日は、そんなこの本を、
推しながら紹介してみたいと思います。
よろしければおつきあいください(^▽^)/

この著者は
かの有名なドイツの文豪ゲーテ(僕も遥か昔に『若きウェルテルの悩み』を、確か課題図書として読んだことしかありませんが)、
・・・ではなく
晩年のゲーテに気に入られ、親しく交わる機会を得た
ヨハン・ペーター・エッカーマンという人物です。
9年間この人物は
ときには毎日のようにゲーテの邸宅に出入りし、
芸術、科学、政治、人生
色々なことを話し合い、
ゲーテからの名言を浴びるように受けました。
「こんなすばらしい自分の体験を、世の人々にシェアせずにはいられん!」
というわけで、書かれたのがこの本です。
本書は日記形式で書かれ、
〇月〇日、〇〇の用事でゲーテの家に行った。〇〇と〇〇がいて、夕食を取りながら〇〇について話した。ゲーテは上機嫌で「〇〇はね、〇〇だよ!」と言った。
というような感じで進んでいきます(すごい記憶力だ!)。
そしてこの中身が、
ゲーテの名言のオンパレード
なんです!
今ちょっと見返しただけでも
「本当に他人の心を動かそうと思うなら、決して非難したりしてはいけない。まちがえたことことなど気にかけず、どこまでも良いことだけを行うようにすればいい。大事なことは、破壊することではなくて、人間が純粋な喜びを覚えるようなものを建設することだからだ」
「やたらに定義したところで何になるものか!」「状況に対する生き生きした感情と、それを表現する能力こそが、まさに詩人をつくるのだよ!」
「詩というものは、人類の共有財産であり、そして、詩はどんな国でも、いつの時代でも、幾百とない人間の中に生み出されるものだ」
「(オリジナリティなるものについて)滑稽千万だ。まるまると太った男をつかまえて、ウシか羊か豚か、どれを食べてそんなに力をつけたのか、などとたずねるようなものさ。もちろんわれわれは素質をもって生れてくるのだが、しかしわれわれが成長していくのは、広い世界の数知れぬほどの影響のおかげであり、この世界から、自分にできるものや、自分にふさわしいものを身につけるからなのだ」
「真理というものは絶えず反復して取り上げられねばならないのだ。誤謬が、私たちのまわりで、たえず語られているからだ」
「いつの時代にもくり返し言われてきたことだが」「自分自身を知るように努めよ、とね。しかしこれは考えてみると、おかしな要求だな、今までだれもこの要求を満足に果せたものなどいないし、もともと、誰にも果せるはずはない」
「結局のところ、忠告を求める者は目先きがきかず、(忠告を)与える者は僭越だということだ。忠告を与えるのなら、自分自身も力をかせることだけに限るべきだよ」
・・・
という感じです。
何かを学ぼうと意気込んで「古典的名著」を読んでも
現代とのギャップがあって難しいと思うのですが、
この本の中のゲーテの言葉たちは
自己啓発本
並みに直接的に刺さってきます(僕にとっては)。
古い感じがしません。
僕がバンドとかやっていたからかなあ。
いや、
絵画、文学、音楽、演劇等のいわゆる「アート」に限らず、
自分を「表現」して世の中をわたっていこうとする人なら、興味をもって読めば響くものがあるんじゃないかと、僕は思います!
もう一つ。
もう一つ僕が興味をひかれるのは、
著者のエッカーマンという人物です。
「序章」に詳しく述べているところによると、
ドイツの小さな町の貧しい家庭に生まれ育ちました。
年の離れた兄二人は、
物心ついたときから船乗りなどになって家を出ており(一人は行方不明)、
一人っ子のように育ったとあります。
子ども時代の生活は親の手伝いが主で、
農作業をしたり、父親の行商に一緒についていったり。
学校には時期を区切って行けるときだけ行き、
どうやら読み書きを覚えたころにはもう14歳。
「こんなことでは、かんじんのゲーテと親しい関係になるまでには、まだたいへんな道のりがあるし、およそどこをつついてもまだそんな気配はさらさらない、と人は思うだろう。私にしてからが、この世に文学とか美術とかいうものがあることさえつゆ知らず(略)」
そんな生い立ちだったエッカーマンは
ひょんなことから写生→美術に目覚め、
学問に目覚め、
とはいっても生活のために役所などの仕事をしたり、
ドイツ解放(←ナポレオンの支配からの)の義勇軍に志願して国外に遠征したり、
20代になってから大学に入ったり退学したりし、
やがて自分の文章を見てもらいにゲーテを訪れたところ気に入ってもらい・・・
と、まあ苦労を経て上流階級の仲間入りを果たしたわけですが、
貧乏で学問から程遠かった子ども時代を彼は嫌なものだと思っていません。
こう言うのです。
「年ごろにもなると、私はさっそく父のお伴をさせられて、村から村へと旅まわりで、荷物運びの手伝いをした。この時期が私の少年時代の一番楽しい思い出となっている」
と。
森や野の野鳥を捕まえたり飼ったりすることはお手の物だったらしく、
ときどきゲーテに、鳥の知識をとうとうと語って感心させる場面も出てきます。
「閣下はなんでもご存じですが、鳥のこととなると子ども同然ですね」
なんて言ってからかう場面もあります(笑)。
きっと、子ども~青年時代の経験が、彼になにか伸び伸びした感性を与えていたのでしょうね。
きっと、貧乏でも善良な親たちだったんでしょうね。
彼自身の作品で名を残すことはなかったけれど、
やったこと(ゲーテの言葉を伝えたこと)はまさに偉業。
なんだかちょっと胸が熱くなりますね。
長々と書いてしまいましたが、
最後までお読みいただき、ありがとうございました!
明日・明後日は塾はお休みをいただきます♨
金曜日(11日)よりまたよろしくお願いいたします!


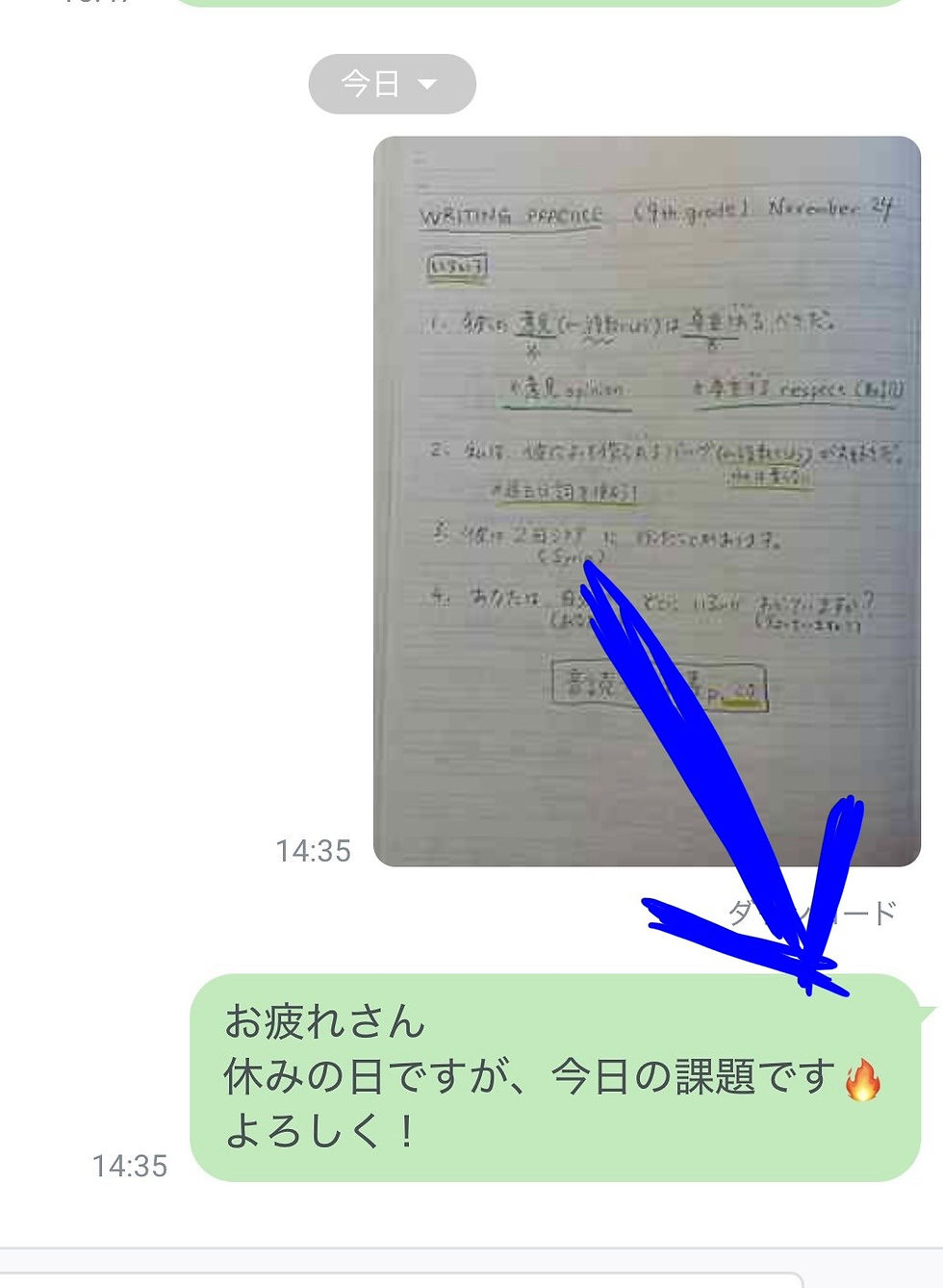
コメント