【仮説】高学年で算数が苦手な子は、〇〇からやり直すべし(?)
- orangejuku
- 2024年6月11日
- 読了時間: 2分
小学生の高学年で
算数に苦戦する子たちに
うんと下の学年からの内容を遡ってやってもらっています。
「ツボ」というか、
効果的な方法を探りながら。
そんな中で気がついたことですが、
そういう子たち、
「時刻の計算」
が全然できないのです。
正確に言えば、
そういうケースに連続して遭遇しているのです。
九九は知っている。
四則計算は一応できる・・・んん?
加減乗除の意味は・・・
小数は・・・う~ん・・・
だんだん怪しくなってしまうのですが、
なんかの形に従って、
無機質にやることには慣れ切っているんです。
でも
「午後6時の1時間15分前は午後何時何分ですか」
とか
「午前12時45分から午後1時10分までは何分ですか」
といった問題に、
まるでトンチンカンな計算を繰り広げるのです。
「生活に困るでしょう?!」
と言いたいですが、
まあ今は困らないのかな。
時刻の計算は、
2年生から3年生にかけて勉強して、
その後の学年で登場することはありません。
もしかすると軽視されているかもしれません。
僕も小学校の勉強は、
そこまで詳しくないのでわかりませんが。
でもこれ、もしかしたら
引き算や足し算を、「具体」を伴ったものとして理解すること
(↑うまく言葉にできませんが・・・)
60を足すとか、ちょっとした「テクニック」を使うこと
など、
算数(数学)の基礎をつくるとても大事な単元かもしれない、
と思う今日この頃です。
ちなみに
「長さの単位」
とか
「重さの単位」
についても、同じようなことが言える気がしています。
たまたまそういうケースに最近遭遇した、というだけですが、
もしかしたら
算数苦手にメスを入れるツボかもしれない!



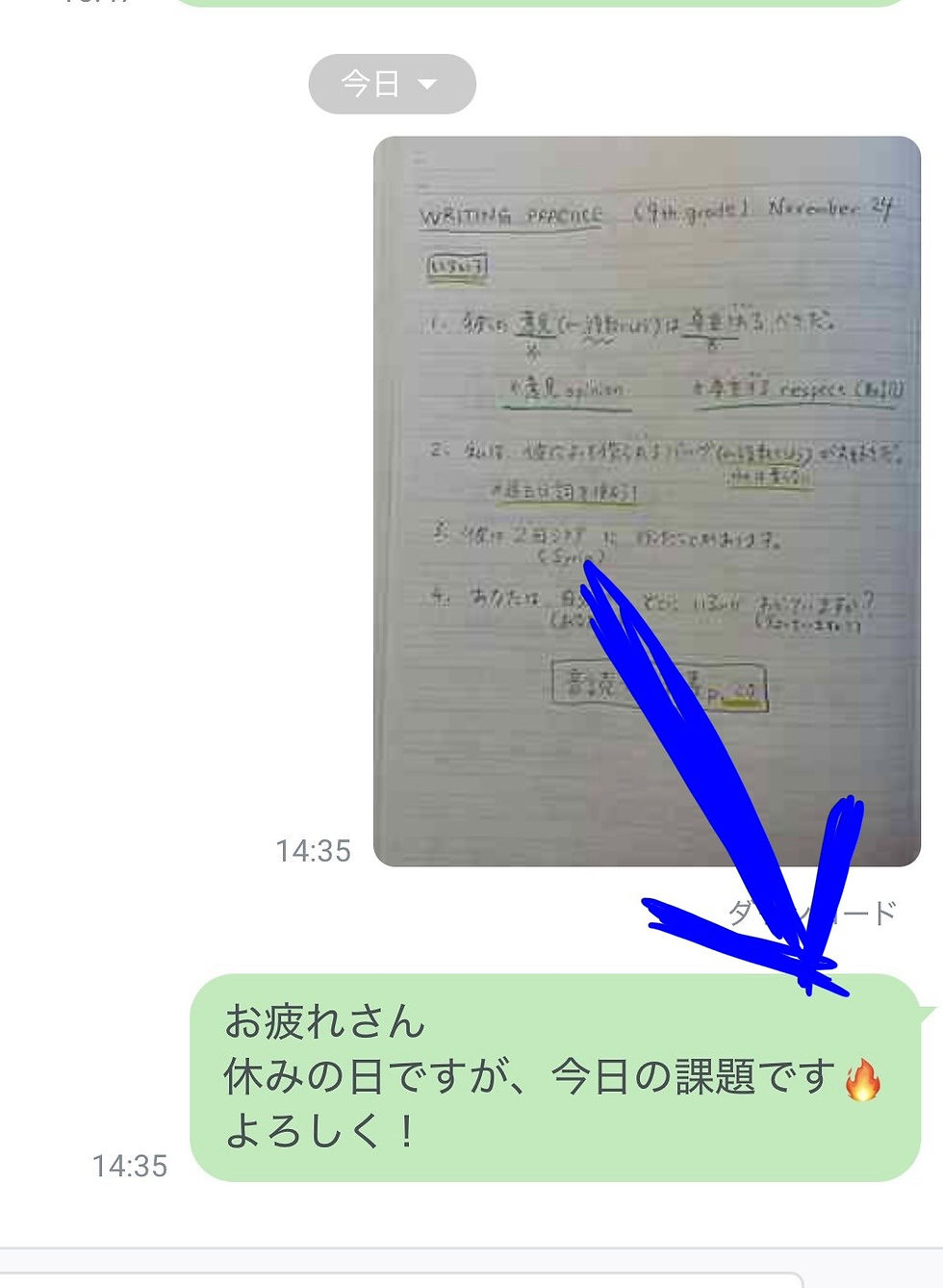
コメント