二項対立
- orangejuku
- 10月9日
- 読了時間: 3分
「三語短文」を通して
子どもたちに文の書き方を教える。
これはとても楽しく、やりがいのあることです。
初めは支離滅裂だった文に、起承転結をつけたり、言葉を補ったりして、
子どもの脳内にぼやーっとあったアイデアを形にしていく。
「物語」をつくっていく。
かっこよく言うと、そんなことをしています。
でも最近、
「物語」って、危険なことなのかも、と思うようになりました。
「言語化」と言い換えてもいいかもしれません。
高校生は、国語の長文読解で、
たぶん「二項対立」というものを習うと思います。
その文章の中に、どういう立場とどういう立場が紹介されていて、
筆者はどっちの立場に立っているか。
その見方で、大体の文章は読めます。
明快で、便利な方法論です。
でも・・・世の中の何かの問題について、たった2つの立場に整理してしまうのです。
乱暴といえば乱暴ですよね。
よくいわれる文章の3つの論理の関係、すなわち
「イコールの関係」(A=B)
「対立関係」(A⇔B)
「因果関係」(A→B)
も、「二項対立」につながりますよね。
で、世界の現実は(なんか偉そうなこと言っていますが)、
たぶんそんな単純じゃないと思うんです。
生態系、人体、化学反応・・・
そして人間社会、経済も。
肝臓は500種類もの機能をもっているそうです。
二項対立の頭では、到底とらえきれないでしょう。
でも人は、単純化されたストーリーをほしがります。
それも生き物としての性かもしれません。
そこで「物語」が出てきます。
政治、宗教、民族、思想、歴史・・・
そんな物語を聞いて、すっきりした気分になったり、「よくわかった!」とか言ったりします。
でもそれは本当に合っているのか?
昔僕も(大学でアラブ・イスラムを専攻したにすぎず、専門家でもなんでもありませんが)
中東の不安定な情勢について
「結局石油でしょ?」
「2000年続く宗教の対立でしょ?」
とか簡単に決めつける人がいると、
「いや、そんなに単純じゃないんだが・・・」
と思って困惑したことがあります(でもうまく返答できず)。
またそれ(わかりやすい物語を求めること)は、
往々にして「敵」を探すことでもありますよね。
自分の生存のために生涯かけて戦うのは生き物の性とはいえ、
政治、宗教、民族、思想、歴史・・・
それらの「物語」(ハラリに言わせれば「フィクション」ですね)の下に、いまだにあまりにも多くの無駄な犠牲が出続けているのが現在の世界ではないでしょうか。
話をまとめます。
素直な感覚で生きている子どもたちに、
論理とか語彙とかを教えることで、
実は彼ら彼女らを硬直化させ、目を曇らせ、愚民化しているんじゃないか
そんな風に思うときがあります。
でも、
せめて、
論理とか語彙を手に入れることが、
二項対立を超えて
現実を正しく見る力につながってくれたら・・・
と思います。



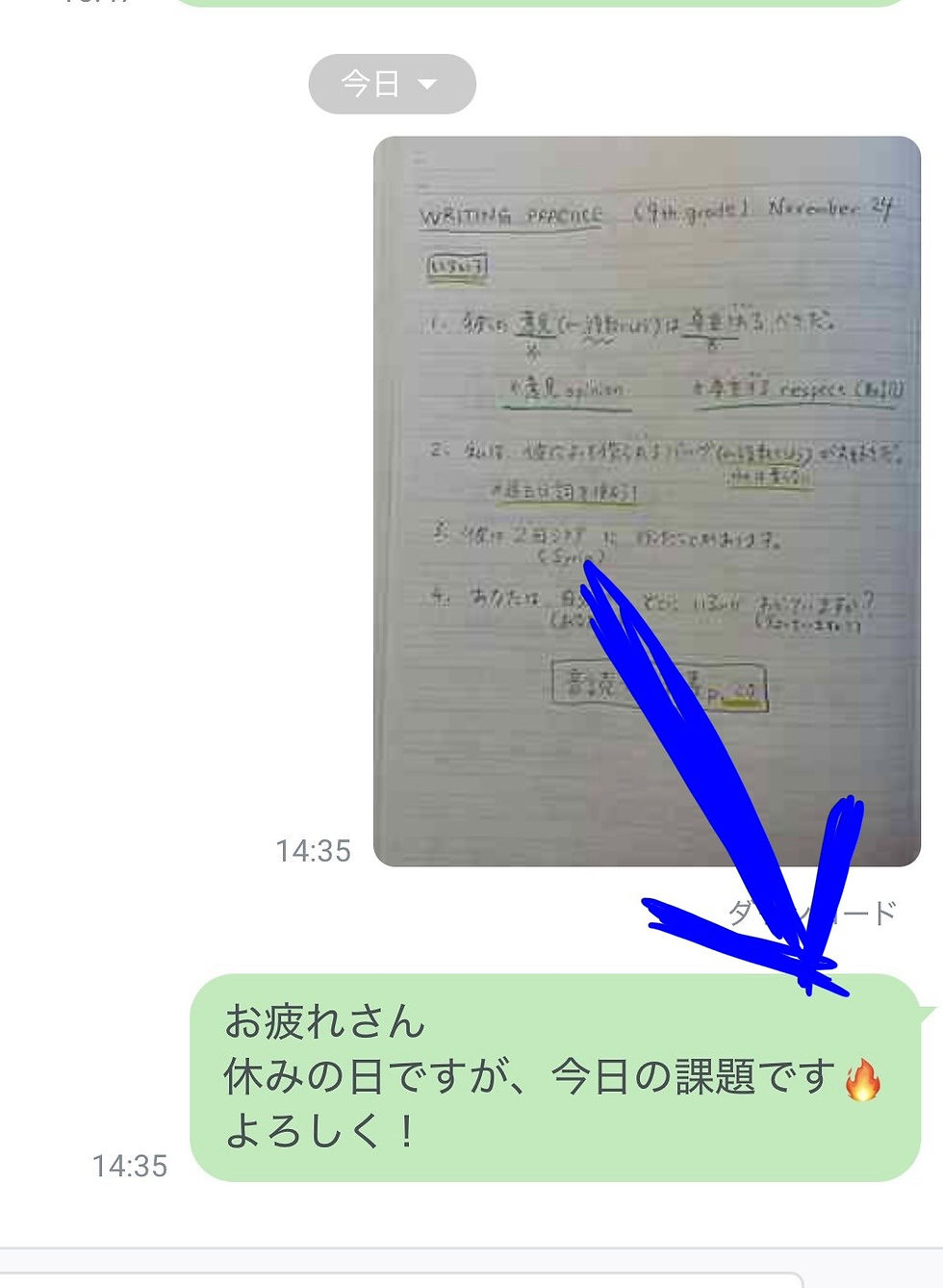
コメント