「勉強の仕方がわかりません」
- orangejuku
- 2021年10月16日
- 読了時間: 3分
この悩み、いつでも結構聞かれます。
最近では大学受験が近づいてきた&英文法について自分のわかってなさに焦りだした高校生からも「勉強の仕方がわからなくて・・・」「宿題が欲しいです」なんて言われました。
この普遍的なお悩み、ちょっと掘り下げてみたいと思います。
一般的に、スポーツでも楽器でも、機械の操作でも伝統工芸の技でも、
習得するためには「ひたすら練習あるのみ」ということになるかと思います。
勉強だったら、問題をたくさん解く、ということになると思います。
何よりも実戦!
まずは量!
何の問題集がいいかとか悩む前に、まずはやってみる!
それ超大事ですね。
その点、塾に来れば問題はたくさん出してあげられます。
プリントアウトすれば何回も繰り返してやることもできます。
本屋さんで問題集をたくさん買うのも、大変ではありますよね。
スマホやゲームや友達とのお喋りに邪魔されずに勉強(=問題をたくさん解く)できる「場」として、ぜひとも塾を活用してほしいと思っています。
しかし・・・
「今日はこれ」、と問題をもらえないと、勉強ってできないんでしょうか?
強力な指導者がいないと勉強できないんでしょうか?
将来それで大丈夫でしょうか?
問題集なら、学校からもたくさんもらっていないでしょうか?
いや、問題もらっても、根本が分かっていなければ(&モチベーションがなければ)、にらめっこするだけにならないでしょうか?
自分は学生だった遥か昔、どうしてたんだろう・・・と考えると、
私は塾には行っていなくて、
問題集を買って問題をたくさん解く、なんてこともあまりしていませんでした。
当時は学校が「自習室」みたいな優れた問題集を配布してはいませんでした。
「自学を毎日提出」なんてこともありませんでした。
どうやって勉強してたんだろう?
たぶん、「ノート(紙の裏)にまとめていた」んです。
書きながら、授業で習ったことを確認していました。
自分で組み立てて理解し直したりしていました。
「まとめノートをきれいに作ることで満足して、肝心の内容は頭に入らないままになっちゃう人」が多いのは、あるあるな話ですが、そういうことにはならないように気をつけてはいました。
この勉強方法はたぶん自己流で、正しいのかわかりません。
人に伝授する自信もありません。
ただ、「大事なところ(本質、ツボ、勘所)は何だろう?」ということは
いつも考えながらやっていた気がします。
そんな自分の体験を参考にしつつまとめると、
①実戦(問題にたくさんぶち当たること)も大事
②本質を自分でつかもうとする勉強も大事
ということになると思います。
両方必要ではないかと思います。
①があれば、学習者も「やった感」を持てるのですが、②の裏付けがないとやはりきついんだと思います。
後者に関して、塾として促す方策は、まだなかなかできていないのが実際ですが。
まあ生徒にも話してみよう。
それではまた来週!Have a lovely weekend !



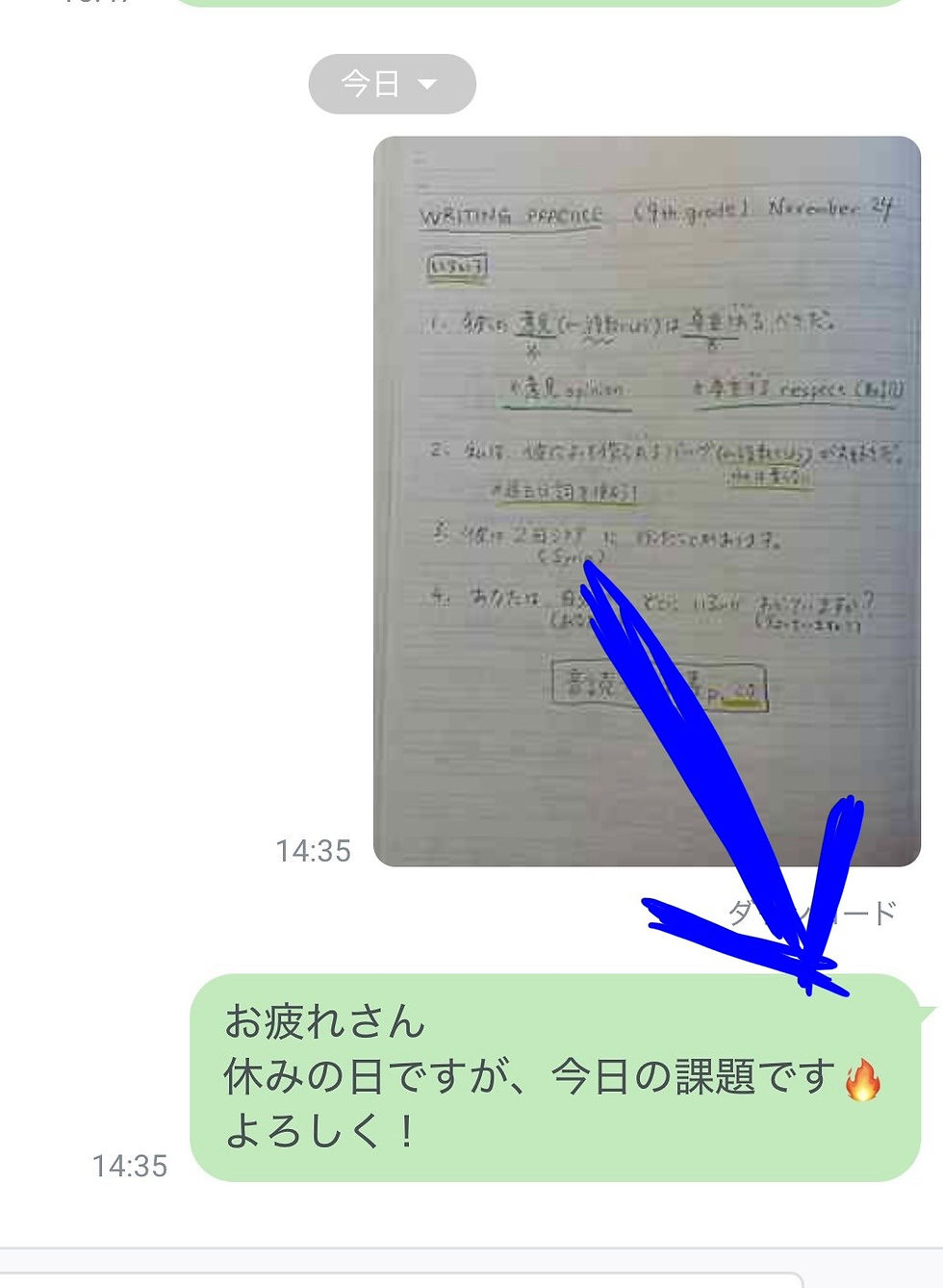
コメント