「将来」とか引き合いに出したら教師の負け。
- orangejuku
- 3月20日
- 読了時間: 2分
☝極論です。
例外的な状況はあると思います。
例えば、
厳しい受験戦争
自分たちを取り巻く貧困
それらが、子どもたち自身にとっても明白に切迫した現実と実感され(もしくはそういう意識のある子どもたちが集まっていて)、
教師の方にも確かな現実観察と強い信念と明確な処方箋があるとき(もしくは話術テクニック的な才能があるとき)、
「お前ら、将来のこと考えろ!」
「社会の現実はこうこうなんだぞ」
「今やってるこれは、将来こういうことに役立つ力になるんだ」
「お前ら、ヌルすぎるっ!!」
etc.
そんな教師の檄は、
響くし力をもつに違いありません。
そうでもない限り、
なかなかやる気を見せない
一向に伸びない
いつまで経っても覚えない
高がそんな状況の生徒にいらだって、
「お前なあ、計算のルールさえしっかり覚えて正確にこなせない人間が、将来社会に出て『こういうときにはあれをやって、こうなったらこうしてください』とかいう指示をちゃんと守れる人間になれると思うのか?」
とか説教かますことは、
間違っていると思います。
・・・何のことはない、5,6年前の僕です。
本当に恥ずかしい。
そして申し訳ない・・・。
教師の側は、善意や熱意もあって、
これに類することを色々言うと思います。
「AIやアジア各国にどんどん後れをとっていくんだぞ?」
「お前ら、そこそこ豊かで不自由ない状況にいるからわかんないかもしれないけどな」
「今の仕事の〇%は将来消滅するんだぞ?」
でも
人は肌で実感できないことは、理屈で言ったってわからないのです。
高いところからのお説教です。
豊かな国に生まれたこと、
それは子どもの責任でしょうか?
大人だって本当に先が読めているんでしょうか?
確かな処方箋を持っているんでしょうか?
肌で実感できないことを理屈でこうなんだと思わせることを、
「洗脳」と言うんじゃないでしょうか?
そりゃ、
切迫感を持った方が力が出る
それは間違いありません。
「俺らタフな環境で育ってきたんで」
というわけですね♪
僕だって僕なりに、
切迫感をもっています。
でもそれが生徒に本当にうまく伝わるか。
そう思えなければ、
切迫感とやらは胸にしまって、
いざというときの糧になるようにと信じて、
根っこの力(基礎的学力)をしっかり分厚く身につけさせるにはどうしたらいいか
そっちをちゃんと考えるべきだと僕は思います。



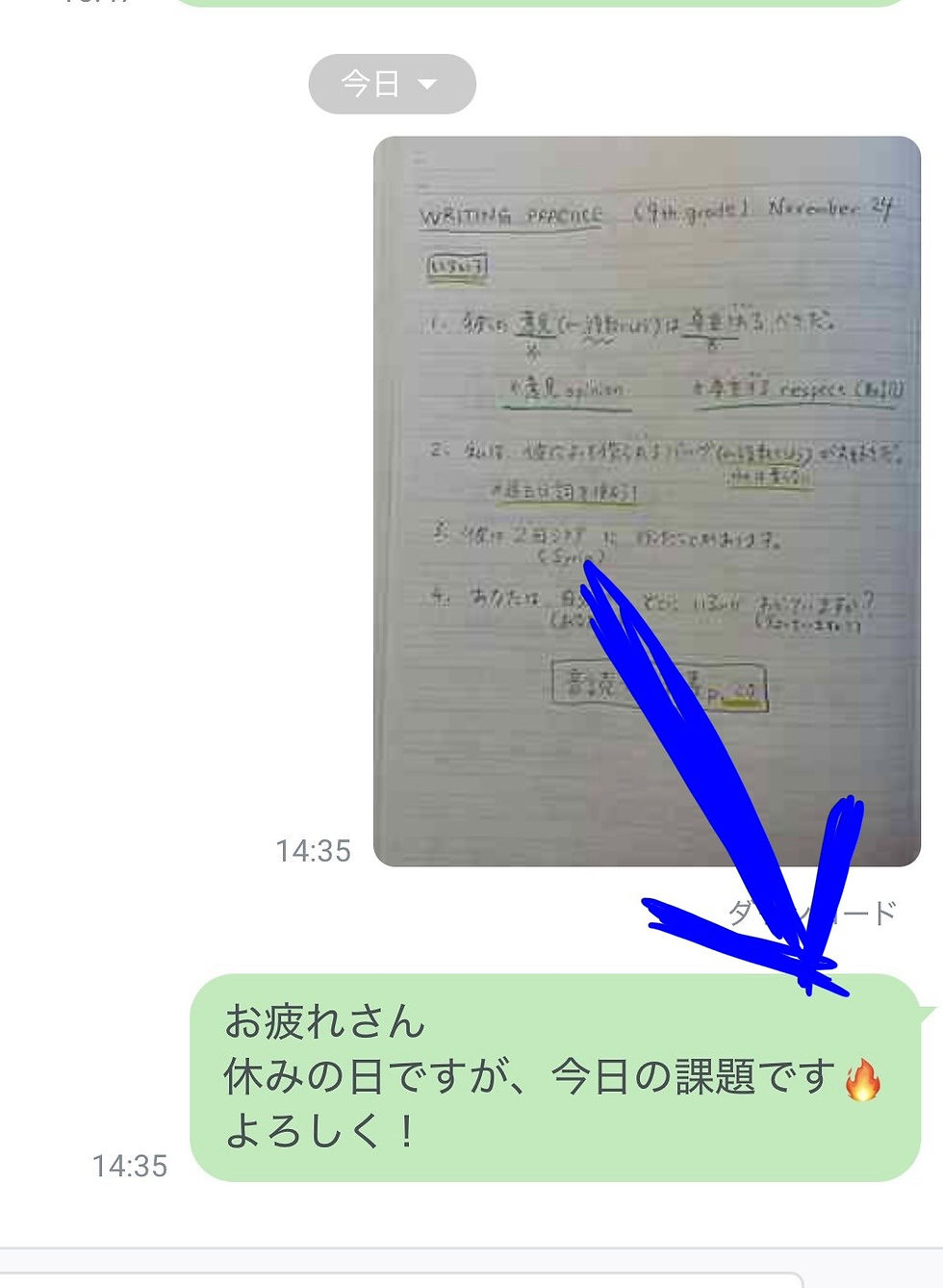
コメント