「習うより慣れよ」、半分正しい。
- orangejuku
- 2023年6月9日
- 読了時間: 3分
更新日:2023年6月10日
勉強に苦戦する子たちにとって、
勉強は、
「指導者があれやれ、これやれ、と言ったものを、言われたとおりにやるもの」
と思っているんだと、思います。
わけもわからぬまま。
この「学び方」は、
何かをマスターするときの仕方として、
決して間違いとはいえません。
多くのスポーツ
楽器
書道や茶道(?)
最初はわけもわからぬまま、指導者や先輩の言う通り
型を真似し、
それを繰り返して練習し、
いつの間にか上達するようになるのだと思います。
私たちが母語を習得してきたのもそういう方法でしょうし、
車の運転だって、車の構造がわかってできるようになるわけではないし、
多くの機械や道具の使い方もそうやってマスターするでしょうし、
仕事も、初めはそうやって学ぶことが多いでしょう。
理論理屈は後からわかる。
(わからなくても一向に構わないものもあります。)
いわゆる「習うより慣れよ」ですね。
「学ぶ」ことの本来の姿ともいえます。
毎日それを身につけるための時間がたっぷりあるとか、
それを身につけなければ生きていけないとか、
上達の道がシンプルではっきりしているとか、
そういう共通点がありそうですね。
一方、いわゆるお勉強の方は
「大事なところ(原理、ルール、法則、勘所、要点)をつかもうとしながら聴く/読む」
ということをしないと、
どうにも身につかないのです。
一般動詞とbe動詞は何が違うんだ?
大正・昭和の歴史は、こういう流れか。
反比例とはつまり、xとyをかけたらいつもaになるってことか。
分子をつくらない、ってどういうことだ?
等々
それが分かれば
その分野の問題の多くが
「あ、こういうことね」となり、
発展的なことや枝葉のことも分かるような、
そういう「大事なこと」。ルール。
そういうものをつかむのが先で、
それを自分に叩き込んで覚えないと
どうにもこうにもならないのです。
「自分に叩き込んで覚える」
の部分は、
先ほど挙げたスポーツや楽器その他もろもろと共通ですね。
そこでは根性も必要でしょう。
でも、その前の段階として、
「大事なことをつかむ」
がないと、勉強の場合は、
・・・う~ん、なんとも苦しい(涙)。
算数、数学、式はあてずっぽう~。
英文、読むのも書くのもあてずっぽう~。
社会も理科もあてずっぽう~。
となってしまいます。
勉強に苦戦する子どもたちに
私が少しでも身につけてほしいのは、
そういう考え方とか、習慣なんです。
「大事なことをつかむ」。
仕事によっては、
そんなことは確かに、必ずしも、必要ではないのかもしれません。
でも、
世の中の職業構造が変わり、
社会が変わろうとする今、
いや、もう少しぶっちゃけて言えば
日本の国力が衰退し、
平和と豊かさが失われ、
子どもたちにサバイバルの力が求められるようになるかもしれない今、
学校を終えて、とりあえずどんな職業に就くにしても、
そのような考え方や姿勢をもって世に出ることは
役に立つはず!
と思うんです。



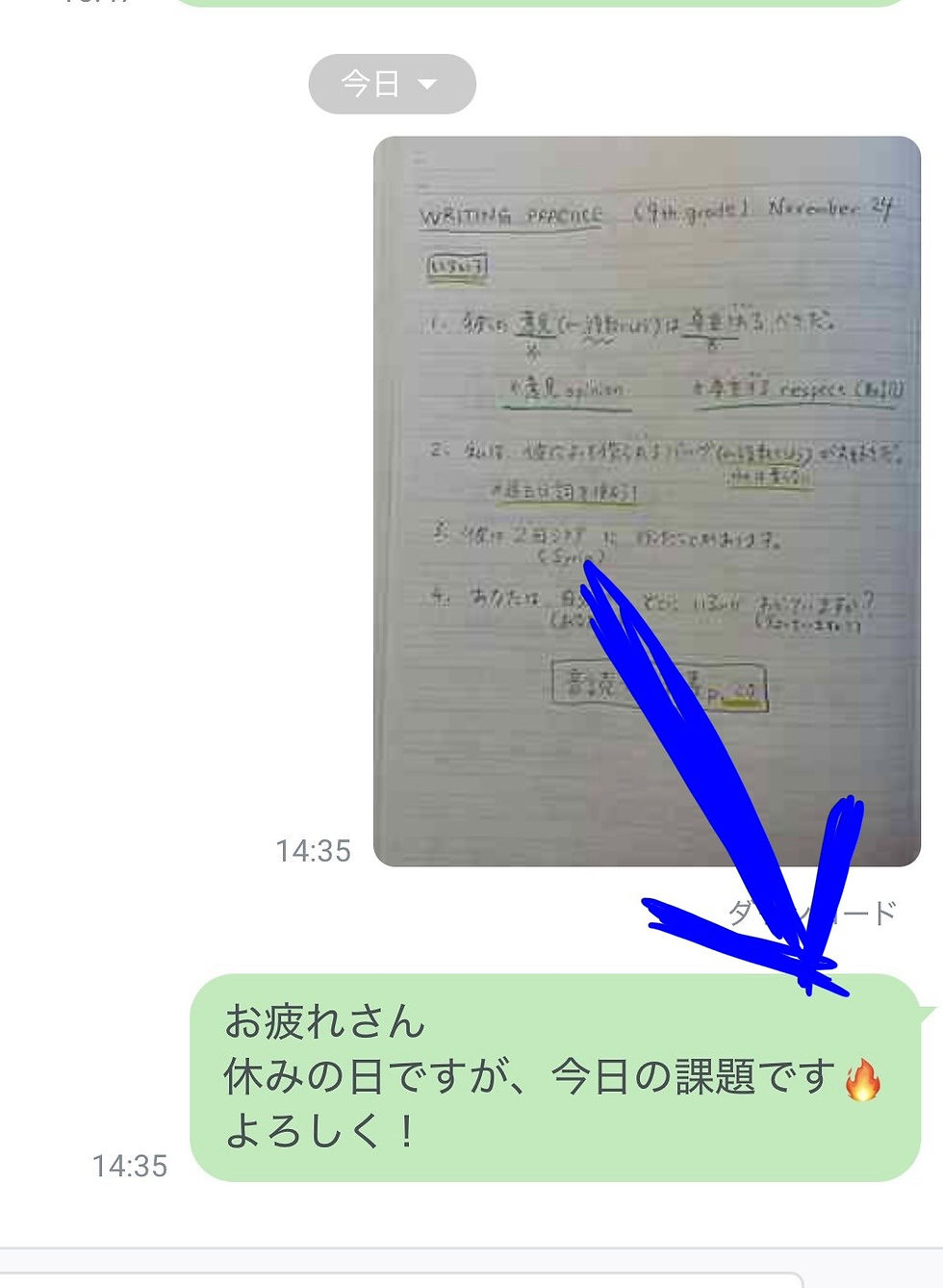
コメント