サインは小2から?
- orangejuku
- 4月9日
- 読了時間: 3分
最近、『ケーキの切れない非行少年たち』(宮口幸治著、2019)という本を読んでいます。
以前結構話題になりましたね(読むのが遅すぎだろう、って感じですが)。
児童精神科医の立場から、少年院で会った多くの経験をもとに、
「境界知能」の子たちについて論じています。
まだ読み途中ですが、
説得力があると思ったのは例えば、
●小学2年生ころから学校の勉強についていけなくなり、サインを出し始める
●勉強以外の多くの点では健常者と同じように生活ができるので、気づかれにくく支援を受けにくい
●「できない」で困っているのに、「怠けている」「ふまじめだ」という印象を受けてしまい、悪循環に陥る
↓
ストレスをためた挙句に最悪の場合非行に走る
といった分析でした。
勉強に苦戦する子たち。
弊塾にもたくさんいます。
それが先天的なものなのか、
後天的なものなのか、
それは素人の僕にはわからないし、軽々しく判断を下すべきでもありません。
ならば心理学の専門家でない僕や、あるいは保護者様には何もできないか?
そうとも思いません。
実際に弊塾には特別支援学級に在籍している子も通っています。
本書の中にこんな事例があります。
「ある少年は、小学校2~4年まで学校によく遅刻していて万引きまでしていたのですが、小学校5年生になってとても熱心な先生に出会えて、”勉強が楽しい””学校が楽しい”と感じるまでになりました。万引きしていた子が学校が楽しい、勉強が楽しいと言い出したのです。きっと小学校5年生の担任の先生にとったらこの子はとても遣り甲斐のある子どもだったはずです」
しかし・・・
「彼の人生は中学に入って急降下していきます。”学校に遅刻””学校をさぼる””悪いことをして逮捕される”などして、少年院に入ることになってしまいました」
「実際に少年に聞いてみたところ、『中学に入ったら全く勉強が分からなくなった。でも誰も教えてくれなかった。勉強が分からないので学校が面白くなくなり、さぼるようになった。それから悪いことをし始めた』と答えました」
「非行化を防ぐためにも、勉強への支援がとても大切だと感じたケースでした」
勉強についていけない(さっぱりわからない)
というのは、
ときに大人が思う以上に子どもに重いもので、
細かな、血の通ったケアを必要とするものなのだと思います。
小学2年生ころからついていけなくなる、
というのも僕の実感として説得力があります。
「塾に通わせる」という方法でなくても、
何か手を打った方がいいと思うし、
僕も引き続き血の通った指導を心がけていかなければならないと思った次第です。



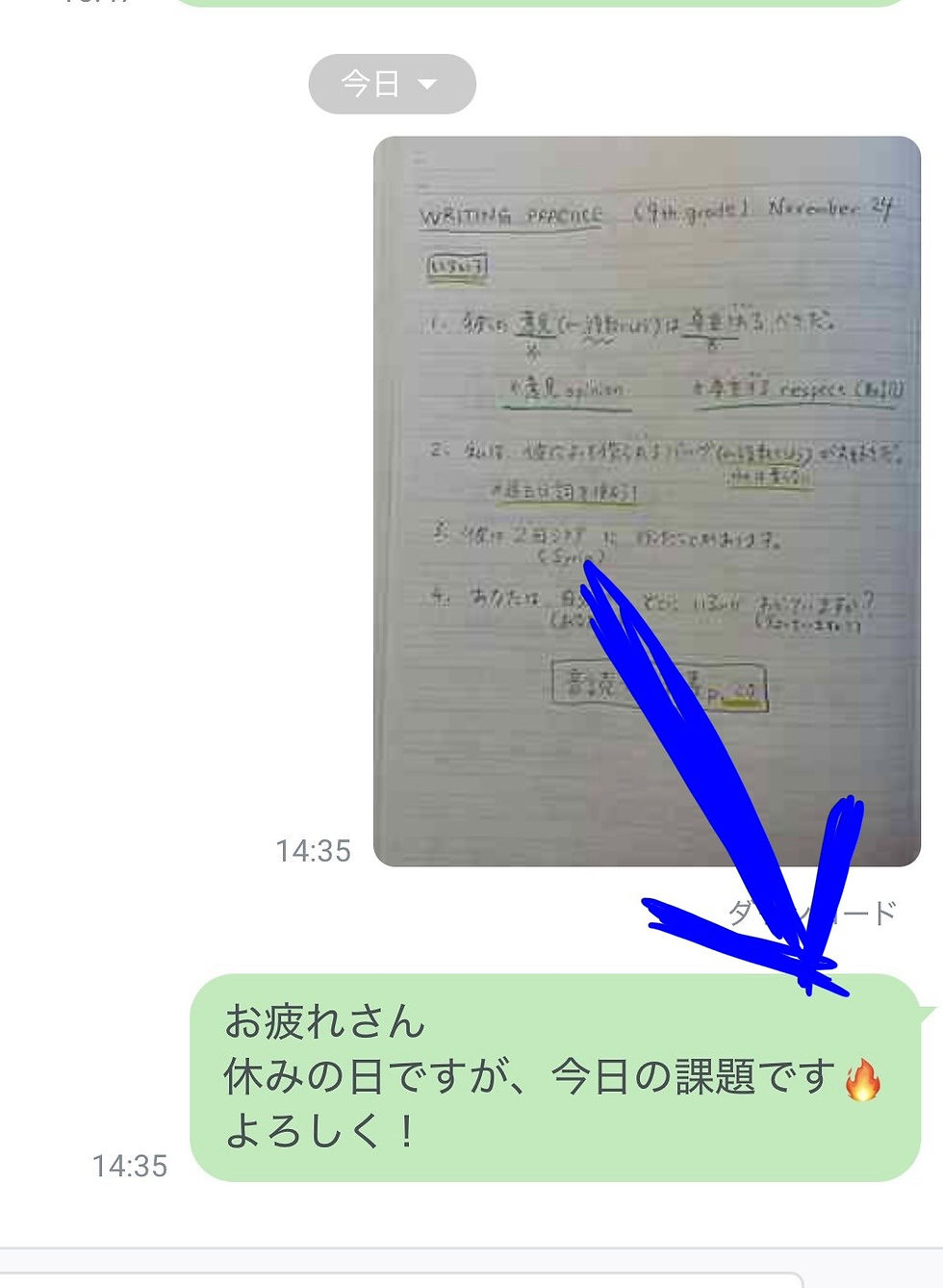
コメント