想像力を育てる。
- orangejuku
- 5月2日
- 読了時間: 2分
国語の問題で定番の質問、
「このときの〇〇の気持ちを答えましょう」。
よく批判の的になります。
「そんなの本人じゃないのにわかるかよ?」
「こういう気持ちだと私は思ったんだけど?」
etc.
僕もどちらかというとそれに近い立場でした。
(僕も国語教育は素人に近いもので。)
「行間を読め」とか、ナンセンスではないのか?
そういうのが「忖度」を育てるんじゃないか?
「書かれていること」に基づいて、冷静に、「論理的」に結論を導き出すことが大事じゃないのか?
・・・
が、
最近ちょっと考えさせられています。
ある物語文(※)で、
ライオンがネコたちのために獲物を取りに駆け出す場面。
(※出典:佐野洋子『空飛ぶライオン』、 『出口式はじめての論理国語』小3レベル、2024より)
その子の読みの浅さに、
「ライオンはどんな気持ちだったと思う?」
と訊かずにはいられなかったのです。
その子の答えは
「獲物を取りに行こうという気持ち」。
う~ん・・・
じゃさ、取りに行こうというとき、どんな気持ちだったと思うかね?
「・・・急いで行こうという気持ち」。
んー・・・
それは間違いじゃないだろうけど・・・
それじゃ、「仕事を果たそうとしている」だけだろう(苦笑)。
気持ちというのは、嬉しいとか悲しいとか怒りとか、
そういうものだろう?
ライオンは、どんなことを思いながら、急いでいたと思うか?
(以下略)
「ライオンはネコたちにカッコつけたかった」
それが一応、僕の「模範解答」でした。
それに気がつかないと、
そのあたりのライオンの行動の描写が理解できないと思われました。
ただ、
意見の押し付けになったら元も子もありません。
かといって、
その浅さを許す気にもなれませんでした。
その子にはちょっと問答を重ねて考えてもらいました。
僕も考えました。
どうすればそういうところに気がついて、言葉にできるか、と。
「獲物を取りに行こうという気持ち」
「急いで行こうという気持ち」
・・・
こう言ってはなんですが、
なんてのっぺりした、
上っ面だけな読みでしょう。
やはり上っ面だけじゃなくて、
想像しなくちゃ。
「心の中のことなんかわかるかよ」
→いや、手がかりならあるものですよ。
「意見を押し付けるんですかー」
→いや、色々な意見があっていいけど、
想像すらしないようでは困る。
算数(数学)の文章題にも、
普段のコミュニケーションにも、
想像力は必要でしょう。
OK, これから俺ももっともっと腰を据えて、
上っ面じゃない
魂の対話
をお前らとしていきたいぜ!



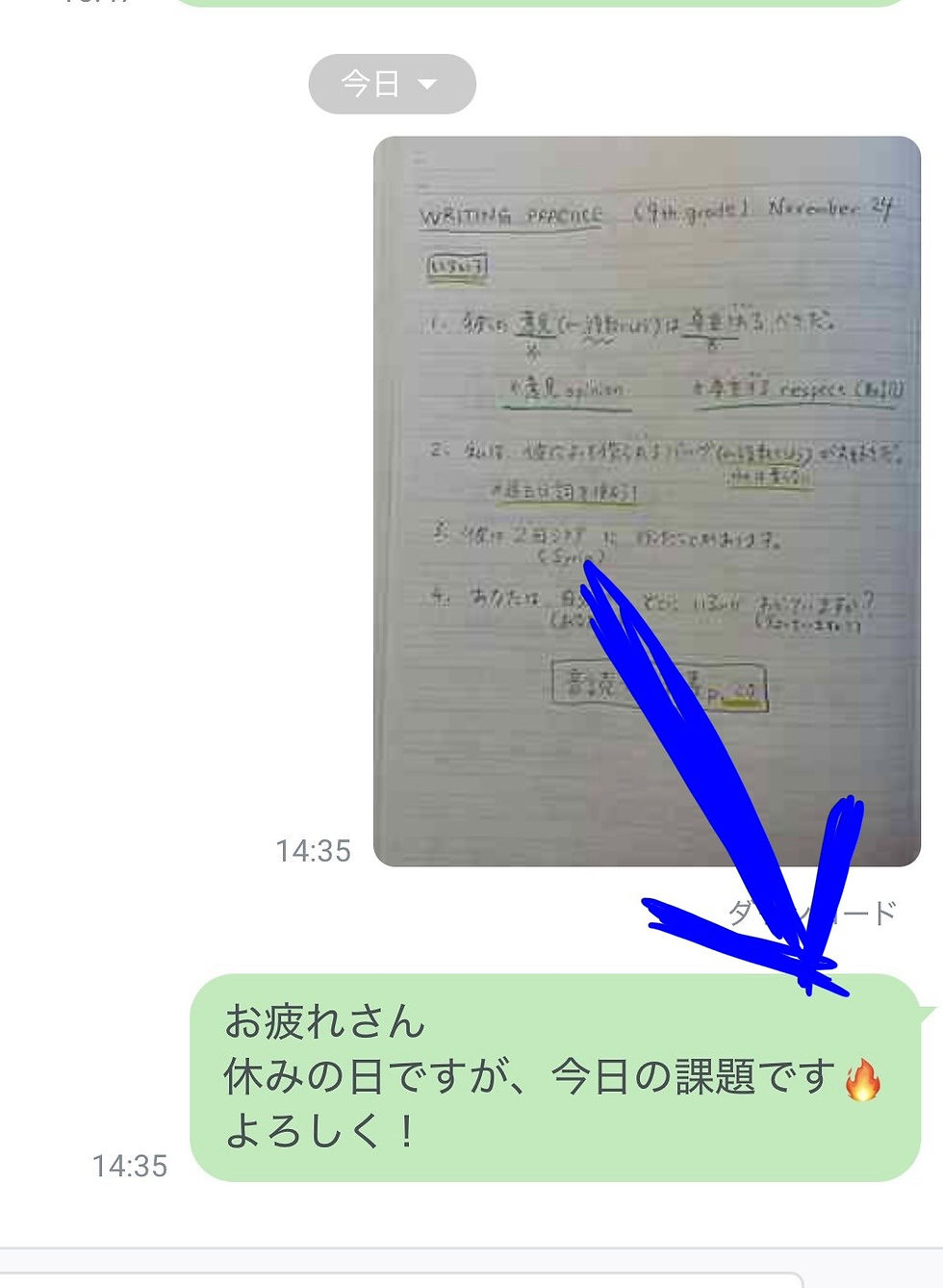
コメント