全国の受験生、がんばれ!!!
- orangejuku
- 1月27日
- 読了時間: 3分
僕は、自分が学生(小~高)だった頃のこと
全然覚えていません。
妻と比べると歴然です。
勉強や受験に関しても、
自分の成績や偏差値の推移
何を使って受験勉強したか
どんな気分・精神状態だったか
・・・恥ずかしながらろくに覚えていません。
教師として教えていることも、
学校や塾で教える側になってから思い出したことが多いです。
きっと、
自分の好きでもないことをゲームのように楽しめず、
心のエネルギーも注げなかったので、
過ぎたらさっさと忘れてしまったんじゃないかと
自分で思います。
世界史の教員になってからは、
これもあまり言うのが憚られますが、
「なんで大学受験ではこんな細かいことを訊く/覚えさせるんだろう・・・」
と思わずにはいられませんでした。
腹が立ちさえしました。
(そういえば大学入学後にも、史学科の教授には、「これまで受験のために覚えてきた知識は、どうでもいいことなんで、捨ててくださーい」としれっと言われ、
「てめーが出題したんだろーが!」
と腹が立ったなあ・・・。)
まあでも大学受験だけじゃないですよね。
世の国家試験とかは、大体そんな苦労をしなければならないのですね。
外国でもたぶんそうでしょう。
なんでこんなこと覚えなきゃいけないんだ?という。
いっぽうで、
社会で、現場で、日々問われるのは、
試験のために覚えたような知識ではない。
本当にその人が役に立つか
有能か、
ということに尽きます。
「試験」と、「現場」の間には乖離があります。
(あったり前の話だろーが、て感じですが💦)
そもそも「受験の苦労」というものは、受動的に丸暗記したりパターン思考を身につけたりしなければならない不毛な作業である。(略)いわば「バカになって」やらなければうまくいかないものである。(略)せめて、その有害性を最小限に食い止めるために必要なことは、「この不毛な勉強をせざるを得ないのは、現代の社会が未熟で不完全であり、自分が生き延びるために仕方なしに行わざるを得ない必要悪である」と、本人が明確に意識できることだ。
(泉谷閑示『反教育論』2013)
だから、
大学受験も(色々な国家試験同様)
みんな辛いけれど、
あともう少し!
「ゲームの攻略」と思って楽しむもよし。
「東京大学物語」の水野遥のように、「この問題おもしろー!」と楽しむもよし。
入学後を強くイメージするもよし。
もう少し、がんばりましょう!
そして、大事なのは、入学してから。
僕の知り合いのある塾長は、
「大学など余熱で受かれ」
と言っています。
受験の辛さを、
いっぱいいっぱいではなく、
余裕をもって乗り越える力。
受験終了後に
大学や社会で発揮する力を取っておけること。
(何年後かの受験生に対して言うべき言葉かな。)
全国の受験生諸君、応援しています。
がんばれ!!!

土曜日(1/25)にツクシを発見しました!いやーもう春だあ!


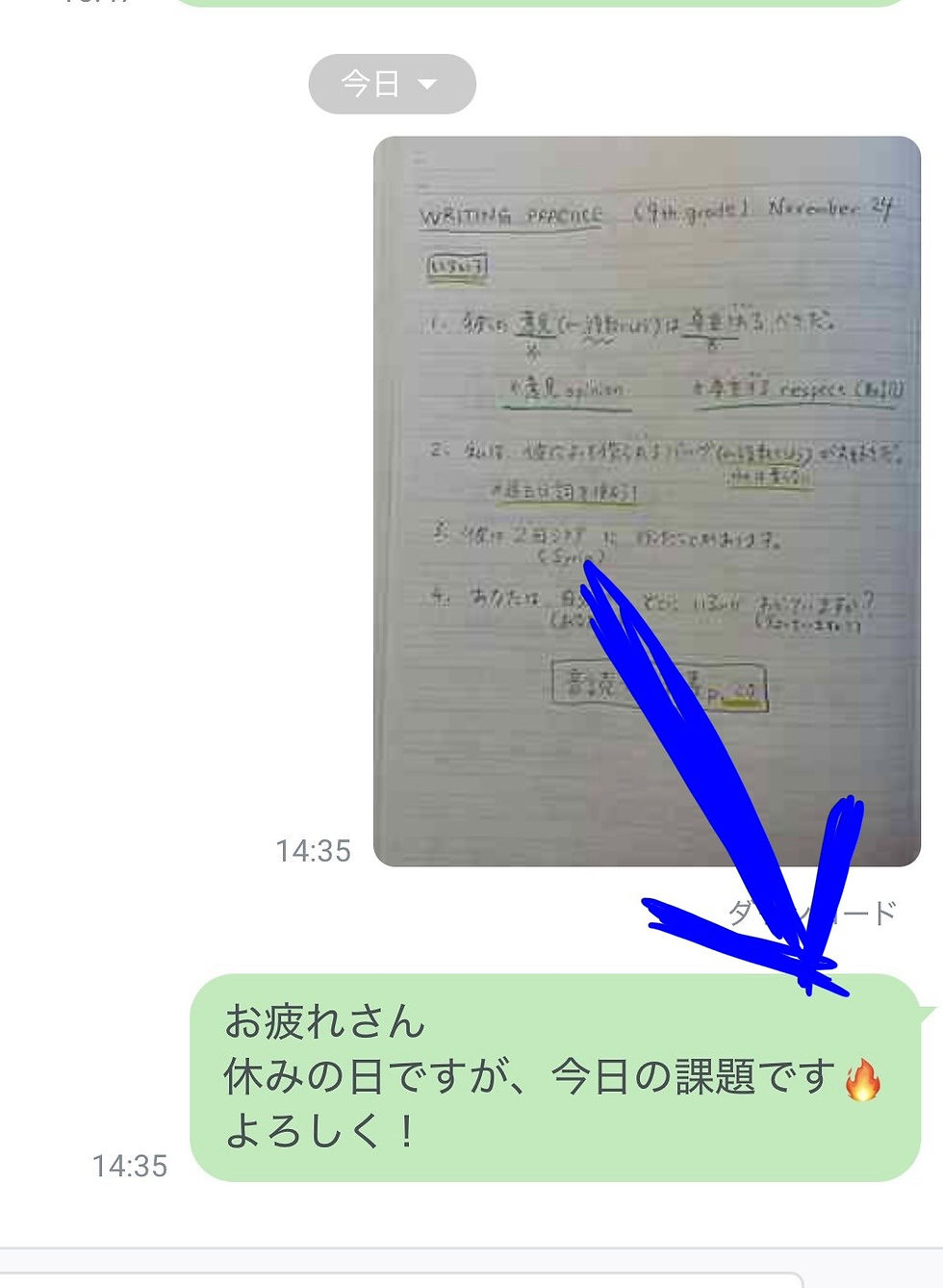
コメント